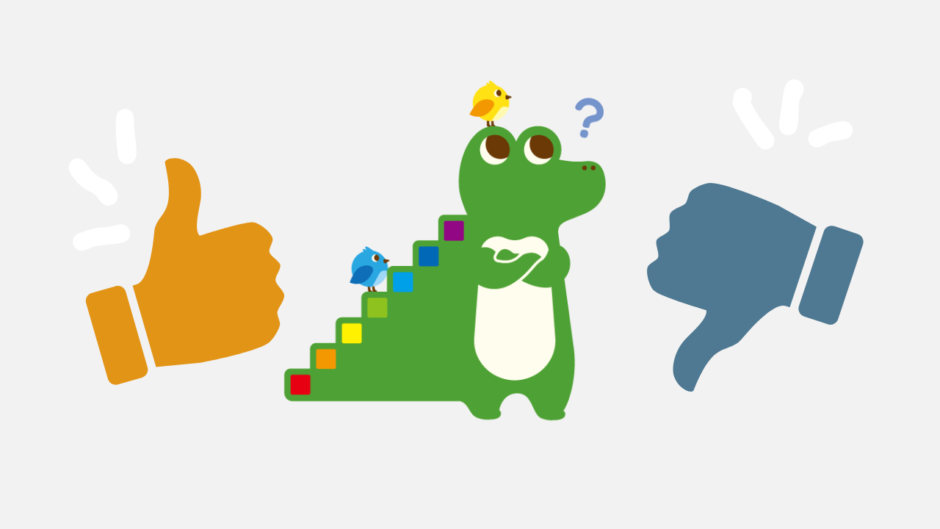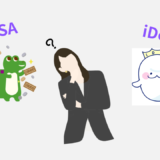この記事で解決できる悩み
・新NISAのことを知りたい
・新NISAは、私にとってどんなメリットがあるの?
・新NISAって本当にいいの?デメリットはないの?
・他の投資となにが違うの?
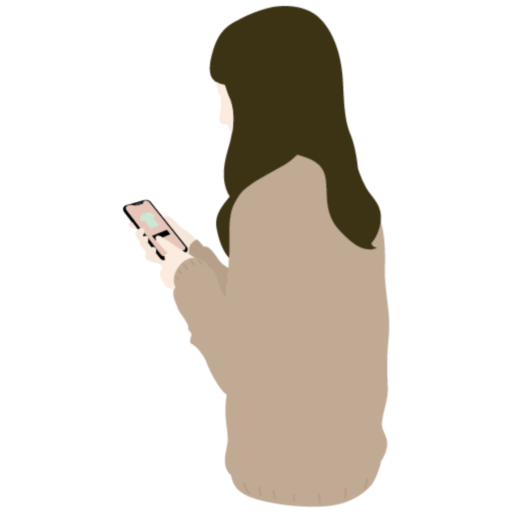
2児のワーママ。投資歴8年目。
投資知識ゼロから始めた投資の含み益は70万円超え。
2024年からスタートした新NISAでは、つみたて投資枠を活用。
毎月1.5万円を積み立てて、早速5千円程度の含み益がでています!
今回は2024年からスタートした新NISAの基本からメリット・デメリットまでお伝えします。
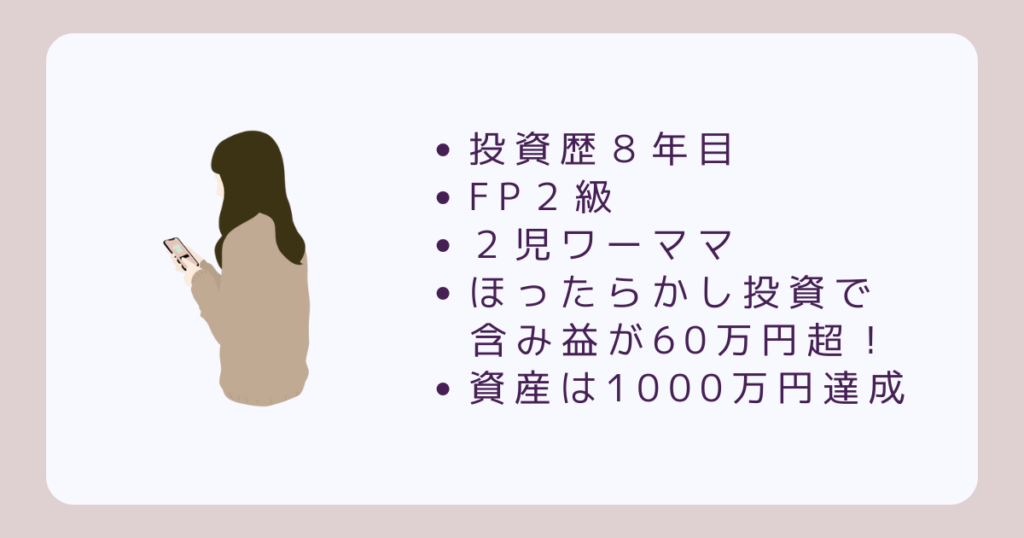
新NISAとは?
「新NISA」は、2024年からスタートしました。
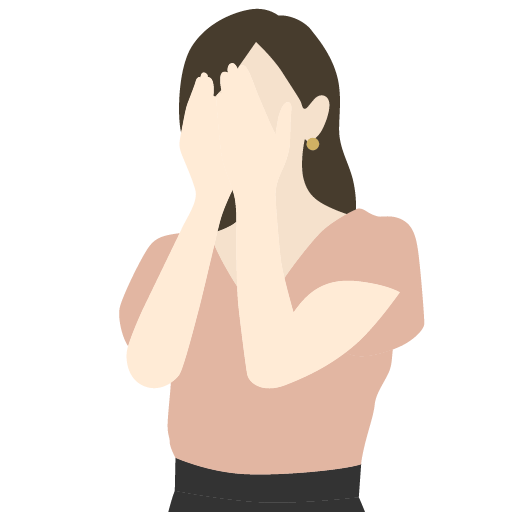
旧NISAから、なにが変わったの?
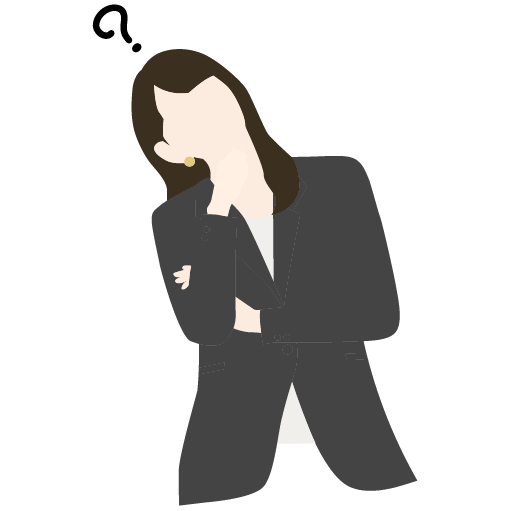
そもそもNISAって、どんな制度??
投資をこれからスタートしたい方に向けて、新NISAを解説していきます。
NISAとは?
NISAとは「少額投資非課税制度」です。
通常、株や投資信託など投資をした場合、そこででた利益に対して約20%課税されます。
しかし、NISA口座で運用すると利益に対する課税はありません。
旧NISAとの3つの違い
「旧NISA」と「新NISA」の違いは、以下の3つになります。
・成長投資枠とつみたて投資枠を併用できる
・非課税保有限度上限額がアップ
・非課税保有期間が無期限に
1つ1つ解説します。
成長投資枠とつみたて投資枠を併用できる
新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を併用することが可能です。
旧NISAでは「一般NISA」と「つみたてNISA」がありましたが、片方のみの利用になり、併用ができませんでした。
新NISAでは、「成長投資枠」「つみたて投資枠」の併用が可能です。
「成長投資枠」と「つみたて投資枠」が併用できるため、投資の目的別で使い分けるなど、投資の幅を広げることができます。
非課税保有限度上限額がアップ
旧NISAに比べて「非課税保有限度額」が増えています。
旧NISAの非課税保有限度額は、一般NISA「年間120万円」、つみたてNISA「年間40万円」でした。
新NISAの非課税保有限度額は、成長投資枠『年間240万円』、つみたて投資枠『年間120万円』と旧NISAに比べて限度額がアップしています。
非課税保有期間が無期限に
新NISAでは非課税保有期間が「無期限」となりました。
旧NISAでは、一般NISAは「5年間」、つみたてNISAは「20年間」と非課税保有期間が決まっていました。
新NISAでは、成長投資枠もつみたて投資枠も非課税保有期間が「無期限」になります。
新NISAのメリット
新NISAには、以下のようなメリットがあります。
・運用益がずっと非課税
・つみたて投資枠で、ほったらかし運用できる
・自由度の高い投資もできる
・100円から投資をスタートできる
・いつでも資産を引き出せる
1つ1つ解説します。
運用益がずっと非課税
旧NISAでは、非課税保有期間に限りがありましたが、新NISAでは非課税保有期間が「無期限」となります。
非課税投資上限額(1800万円)までであれば、運用益はかかりません。
毎月5万円で30年間積み立てると、1800万円することになります。
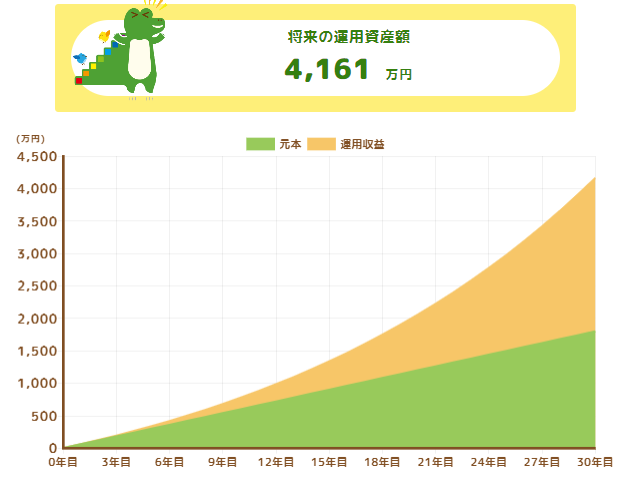
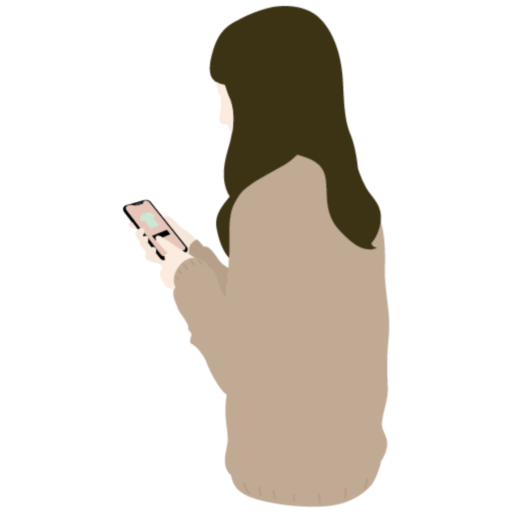
利回り5%とすると、1800万円が4000万円になります!
つみたて投資枠で、ほったらかし運用できる
つみたて投資枠を活用すると、ほったらかしで運用することができます。
ほったらかし運用をするには「長期・積立・分散」に適した銘柄を選ぶことが大切です。
つみたて投資枠での取り扱い銘柄は、金融庁が設けた基準を満たす「長期・積立・分散」投資をするのに適した投資信託です。
ほったらかし投資を考えている方は新NISAの「つみたて投資枠」を活用しましょう。
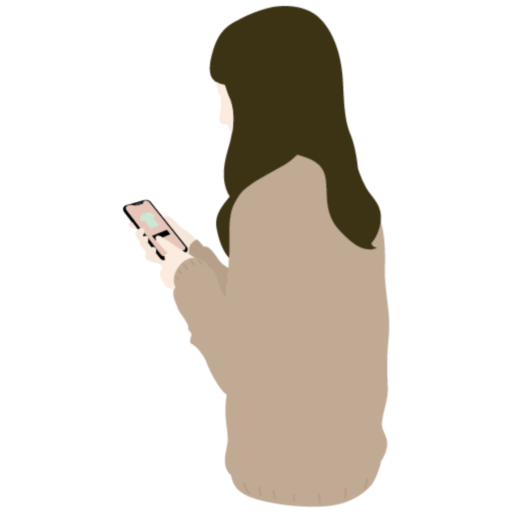
ほったらかし投資は、忙しい方や投資初心者さんなど、投資に時間を割けない方におススメです。
自由度の高い投資もできる
新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を併用することができます。
成長投資枠の取り扱い銘柄は、国内外の株式・REIT・ETF・投資信託と、つみたて投資枠よりも選べる銘柄の幅が広くなります。
投資タイミングも「一括」「つみたて」と選ぶこともできるため、自由度の高い投資もすることも可能です。
100円から投資をスタートできる
新NISAは、証券会社によって100円から投資をスタートすることができます。
SBI証券や楽天証券など、少額から投資をスタートできる証券があります。
少額の投資は増えるスピードがゆっくりですが、投資を長期間行っても生活費に影響がでることがありません。
投資をしたいけど、余裕資金が限られている方にも新NISAはおすすめです。
いつでも資産を引き出せる
新NISAは、運用している資金を自由に引き出すことができます。
増えたお金は、教育資金や住宅ローン・車の購入など、いろいろなタイミングで活用したくなります。
そのためには、必要なタイミングで引き出せることが大切です。
新NISAは引き出すタイミングを自由に選ぶことができます。
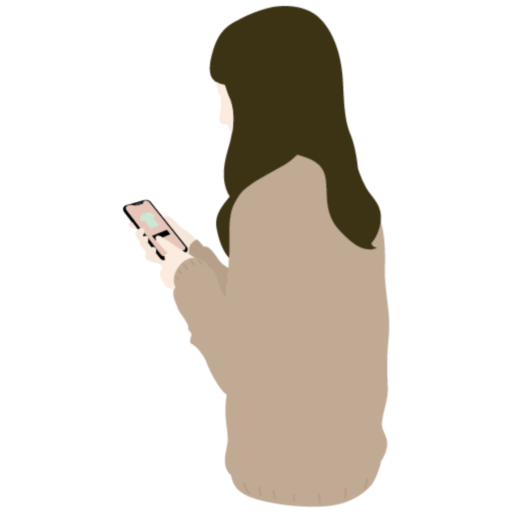
引き出した分の投資枠は翌年に「投資可能枠」として復活させることができます!
新NISAのデメリット
新NISAには、以下のようなデメリットがあります。
・元本割れのリスク
・損益通算・繰越控除ができない
・旧NISAからロールオーバーできない
・売却の判断が難しくなった
・未成年者の利用ができなくなる
1つ1つ紹介します。
元本割れのリスク
新NISAは、他の投資と同様に元本割れのリスクがあります。
日々株価は変動しています。
市場の状況によって株価はマイナスにもプラスにもなります。
新NISAだけでなく、投資は元本割れリスクがあることを理解した上でスタートしましょう。
損益通算・繰越控除ができない
新NISAは、旧NISAと同様「損益通算」と「繰越控除」ができません。
「損益通算」同じ年にでた損失と利益を相殺することで、利益にかかる課税を少なくします。
「繰越控除」ある年に所得が赤字になっても、その後最大3年間にわたり利益と損失を相殺することできる制度です。
例えば、ある年に銘柄Aで「+5万円」で利益確定、銘柄Bで「-10万円」で損失確定したとします。

新NISAは、損益通算・繰越控除が適用されないため損失を活用することができません。
旧NISAからロールオーバーできない
旧NISAから新NISAへ資産の移管(ロールオーバー)をすることができません。
そのため旧NISAで購入した商品を継続して運用することができなくなります。
旧NISAで購入した商品は継続運用することができないため、非課税保有期間内で売却しましょう。
売却の判断が難しくなった
新NISAは非課税保有期間が無期限になったため、売却の判断が難しくなりました。
旧NISAは、非課税保有期間に限りがありました。
そのため、保有期間の期限を売却のタイミングにすることができました。
新NISAは、非課税保有期間が無期限のため、投資目的がないと売却タイミングに迷いやすくなりました。
投資できる銘柄に制限がある
旧NISAに比べて新NISAは対象となる銘柄が限定されています。
新NISAで投資できない銘柄
・信託期間20年未満の投資信託
・毎月分配型の投資信託
・高レバレッジ型の投資信託
新NISAは、旧NISAで購入していた銘柄が購入できないことがあります。
未成年者の利用ができなくなる
新NISAは、未成年者の利用ができません。
旧NISAでは「ジュニアNISA」で子ども名義で投資を行うことができました。
新NISAは「18歳以上」が対象となるため、子ども名義で資産形成することは出来ません。
新NISAの活用方法とデメリット対策
デメリットを見ると不安も出てきますが、デメリットの対策方法もあります。
対策を方法も確認しておきましょう。
投資の目的・目標額を決める
投資の目的や目標額を決めましょう。
投資の目的や目標額を決めておくと、引き出すタイミングも決まるため売却の判断を迷ったり、誤る可能性が低くなります。
投資の目的や目標額を設定しておきましょう。
長期で運用する
新NISAは、時間をかけて長期目線で運用することを考えましょう。
短期で利益がでるものもありますが、その分リスクも大きくなります。
「ほったらかし投資をしたい」「着実に増やしていきたい」という方は、10年以上を目安に運用するのがオススメです。
長期で運用することで損失のリスクを減らすことができます。
余裕資金で運用する
投資は余裕資金で運用しましょう。
すぐに必要になるお金で投資すると、支払いができないなど生活が立ち行かなくなる可能性もあります。
投資をスタートする時、まずは「生活防衛資金」をつくるのがオススメです。
生活防衛資金は3~6ヵ月分の収入と言われています。
生活防衛資金をつくった上で、投資は余裕資金で行いましょう。
万が一、損失がでたときも生活に影響がないため安心です。
投資は、当面使う予定のない余裕資金で運用をしましょう。
新NISAを上手に活用しよう!
新NISAには、メリット・デメリットどちらもありますが、自由度が高く使いやすくなっています。
またデメリットは対策することでクリアできるところもあるので、自身に合うメリットがあれば、ぜひ新NISAを活用してみましょう。